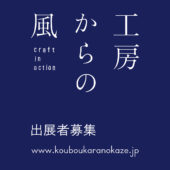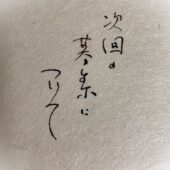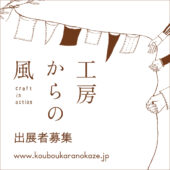-
新着情報
- 2025/04/26 director's voice 機会
- 2025/04/05 director's voice 投函しました
- 2025/03/25 director's voice 「サクラ咲く」通知を
-
月間アーカイブ
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年2月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年6月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年3月
- 2022年1月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年6月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年5月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
2025年4月の記事一覧
「募集・選考/工房からの風」New
director's voice
コメントする
投函しました
ニッケ鎮守の杜では、13本のソメイヨシノがほころび、満開を迎えました。
金曜日夕刻、選考結果を投函いたしました。
昨今の郵便事情では、到着まで数日かかります。
ご遠方の方もいらっしゃいますので、もし12日までに郵便が届かない方がいらっしゃいましたら、
事務局までお問い合わせくださいませ。
0473702244
フレッシュな作家からベテラン作家まで。
充実の出展作家が決定しました。
ご応募くださいました皆様。
お知らせなど情報を広げてくださいました皆様。
誠にありがとうございました。
ここから、出展作家は日々自己刷新してゆかれ、現時点以上の素晴らしいお仕事を見せてくださることと思います。
10月25日、26日の土日。
今から手帳にチェック、お入れください!
第23回工房からの風
始動しました。
director's voice
コメントする
出展作家2次募集開始!
出展作家2次募集始まります。
出会いの風が運んでくるものを、ぜひ掴んでほしいと思います。
開催日: 2025年10月25日(土)26日(日)10時~16時
応募期間: 2025年3月21日(金)~3月31日(月)必着
1次で素晴らしい出展作家を選出しており、2次では加えて25作家を選出いたします。
出展することで、まずは50+α人のすばらしい同時代をものづくりとして生きる作家と 出会え、切磋琢磨できる関係性を生み出せます。
このことも、工房からの風の大きな魅力だと思います。
2次では特に、陶芸、金属、布関連、その他ジャンルの作家の方のご応募をお待ちしています。
もちろん、他のジャンルの方も奮ってご応募ください。
昨年出展された作家はご応募ができませんが、それ以前の方はご応募いただけます。
また、「工房からの風」が適していると思われる作家をご存じでしたら、ぜひ募集開始をお知らせいただけましたら幸いです。
今秋10月25日(土)26日(日)
実りの野外工藝展となりますように。
その第一歩が、可能性、ちから、豊かな作家の方からのご応募です。
詳しくは、HPの以下をお読みください。
https://www.kouboukaranokaze.jp/cia/about/#point
director's voice
コメントする
選考結果を投函しました
2025年10月開催予定の第23回「工房からの風」1次募集の選考を終えて、ご応募くださいました皆様へ選考結果通知を投函いたしました。
募集人数に対して約4.4倍のご応募をいただきました。
内容的にレベルの高いご応募でした。
ご応募くださいました皆様へ感謝申し上げます。
応募用紙に文章を綴り、写真を整える一連のものごと自体が、ご自身の仕事を客観視し、プレゼンテーション力を磨く機会になると思います。
今までの中には、1次で選外になられて、2次には見違えるようなプレゼンテーションをされて選考通過し、当日に豊かな結果を実らせた方も数名いらっしゃいます。
いずれ選考に正解はなく、様々な要因、タイミングもあることと思います。
選考通過された方は、この機会を最大限に生かすべく準備をスタートなさってください。
選外になられた方もあらためてご自身のお仕事を振り返られたり、今後を見据えて、ご自身にとってよき機会を見出していただけることを願っております。
尚、2次募集は
2025年3月21日(金)~3月31日(月)必着
となっております。
2025年の「工房からの風」どうぞご期待ください。
director's voice
コメントする
絶賛受付中
1次募集受付中です。
2次募集もあるから、まだいいかな。
と思っている方、1次での応募をお勧めします。
なぜなら、同ジャンルや同じ作風の方が1次で通過していた場合、2次では選外になる可能性が高いからです。
展覧会全体の構成としてはジャンルや作風の重複はなるべく避けたいと思っています。
なので、優秀な作家とお見受けしても、選外通知を出さざるを得ないのは、当方も心苦しいのです。
ということのほか、今年中に来年秋の大きな仕事の予定が立つのも制作予定としてもとても良いと思います。
18日(水)必着です。
(郵便は以前より到着までに時間がかかります。
宅配便も、お歳暮、クリスマスの繁忙期で遅れる事例が多発していますのでご注意ください)
素晴らしい出会いをお待ちしています。
director's voice
コメントする
募集始まります!
次回、第23回「工房からの風」の出展作家の募集についてお知らせします。
〈開催日時〉
2025年10月25日(土)・26日(日)10時〜16時
〈場所〉
ニッケコルトンプラザ屋外会場
〈応募期間〉
1次募集:2024年12月1日(日)~ 18日(水)必着
2次募集:2025年3月21日(金)~3月31日(月)必着
今年度から変更となった点は、出展した翌年のみ応募ができないことです。
(昨年までは2年間応募ができませんでした)
2023年に出展された方もご応募いただけますので、意欲的なご応募をお待ちしています。
詳しくは、プロフィールのリンクから、趣旨・応募要項をお読みください。
→ click
1次では最大25名を決定いたします。
1次で出展が決定しますと、2025年の制作・発表スケジュールが立てやすくなると思います。
また、とらえ方によっては、10か月をかけて作家として成長する機会にすることも可能です。
1次で決定した作家と同じジャンルや近いお仕事の場合、2次では選考に通りにくい場合があります。
1次で選考に入らなかった場合でも、2次に再応募することも可能です。
1次への意欲的なご応募をお待ちしています。
director's voice
コメントする
出展作家募集
今年度の第22回「工房からの風」への出展作家を募集します。
全50-60作家での構成を予定しています。
年末に行った1次募集では、27作家の出展が決まっています。
今回の2次募集では25作家以上を募集します。
詳しくは、募集要項をお読みください。
→ click
1次で決定している作家のジャンル構成は、以下となります。
陶磁 5
ガラス 3
染織布 4
木 5
金属 3
装身具 3
革 3
その他 1
計 27
遠方ですので、大変かと思いますが、北海道、九州、四国、沖縄からのご応募もお待ちしています。
どのジャンルからのご応募もお待ちしていますが、特に器の陶芸、ガラス、染織、金属装身具、そして、「その他」で、魅力ある作家の方との出会いを切望します。
ご応募は、3月1日~20日必着。
郵便到着が遅くなっておりますので、ぜひお早目のご応募をお待ちしております。
director's voice
コメントする
よき機会に
第一次募集の選考を終えて、結果を投函いたしました。
ご応募くださいました皆様に心より御礼申し上げます。
今回、大変質の高い応募を多くいただきました。
コロナ禍前の2019年以来の一次募集を、実行できてよかったと思いました。
「新鮮な作り手は果実のように生まれてきます」
まさにこのフレーズのような作り手の出現を感じました。
25名を選ばせていただくのは大変難しく、27名の作家に選考通過通知を投函いたしました。
(これによって2次選考通過作家数を減らすことはありません。
2次でも25名以上の作家を選考予定です)
通過された作家の方々は、せっかくの豊かな準備期間をぜひに生かしてください。
さっそくに年明けからでもスケジュールを構築して、ミーティングなどもご検討ください。
:::
今日は、選外通知を受け取られた方に向けて特にお書きしたいと思います。
選考通過作家よりも、かなり多い数の方が選外通知を受け取られます。
とはいえ、決して愉快なことではないことと思います。
ご応募くださったお気持ちに添うことができませんでしたこと、心苦しく思っております。
大前提として、選考は力量の優劣のみの結果ではありません。
「工房からの風」という野外展を構成するイメージを抱きながら、そこになるべく合致する作家を選出したいと思っています。
そして、とても惹かれる作品写真であっても、バリエーションや出展数、現在の制作状況、
今後の方向性などを総合的に考慮して、2024年の出展が作家と「工房からの風」双方にとってよいかも考えます。
ジャンルのこともあります。
たとえばどんなによいと思うご応募であっても、同ジャンルばかりで構成することはできません。
1次としてのおおまかなジャンルごとの人数を考えていますので、それを超えた場合は見送らざるをえない作家の方がいらっしゃいました。
:::
と、いろいろ書きましたが、それは気休めや慰めや言い訳ではありません。
まず、応募用紙に向かい、ご自身の作品写真を整え、ご自身の制作を他者に伝えることを実行したこと。
素晴らしい経験だったと思います。
ご自身にエールを送ってほしいと思います。
通った、落ちた、という結果だけをみてはもったいないと思います。
そして、「工房からの風」が今のご自身に合っているか。
それもぜひあらためて考えてみてください。
機が熟して出展したほうが、きっと実りがあります。
「出た」という経験だけが残るより、「出た」ことが次につながるものであってほしいと願います。
そのような機会、タイミングに向けて、ぜひ、ご自身のお仕事を整え、進化、深化させて、よりよいプレゼンテーションをしていただきたいと思います。
それが、「工房からの風」なのか。
そして、そうだとしたら、そのタイミングがいつなのか。
二次のタイミングかもしれませんし、来年なのかもしれません。
いずれ、前向きにとらえていただきたと思います。
:::
「今回の応募が、ご自身の制作、発表の在り方を考えるよき機会となった」
そのように思うことができるのは、ご自身の力のみです。
ぜひ、今後の制作、活動に生かしていただきたいと願っています。
あらためて、ご応募をありがとうございました。
director's voice
コメントする
一次募集について
2024年第22回工房からの風
出展作家の一次募集が12月1日から始まります。
HP運営会社の関係で正式公開が11月27日月曜午後になりますので、
公開内容を、一足先にこちらで記しておきます。
ブルーブラック太字の部分が特に新たな記載です。
一次で出展が決まると、2024年の予定が立てやすくなります。
また、準備が早く始められて、お仕事の成熟度が高まるように思います。
尚、一次で選外となっても二次への応募も可能です。
一次選外で、お仕事やプレゼンテーションを見つめ直し、二次で選考を通過して、よい出展経験をされた作家の方もいらっしゃいます。
もし、出展を希望されていらっしゃいましたら、ぜひ、一次からの応募をおすすめいたします。
意欲的なご応募、お待ちしております。
+++
●趣旨
素材の恵みと、それを生かす人の技術と美の感覚によって形づくられたもの。
現代の暮らしに響く工藝・手仕事・クラフトを柱として企画しています。
「craft in action」と名付けたのは、作家自身が作品を展示して販売する
ということを通じて、素材のこと、技術のこと、表現のこと、使い方のこと・・・
といった売買だけではない、作り手と使い手と伝え手の交流を願ってのことです。
企画をする上で目指しているのは、より有意義で手ごたえ豊かな工藝・クラフトの展覧会です。
新鮮な作り手と使い手と伝え手が集まってくる出会いの磁力のある場づくり。
展覧会への準備体験が、作り手の制作を進化させていくような展開。
自由で和やかな雰囲気の中にも、個々の上質で意欲的な試みが行われる野外展。
約50の個展が集まったかのような濃密さ。
展覧会全体のプロデュースと共に、個々の作り手と企画者が折衝を重ね、
各ブースでの展開を深めていきます。
来場者との出会いはもちろんですが、「工房からの風」に共に出展することによってつながる
作り手同士の出会いは、毎回、出展者の大きな喜びになっています。
この企画は、日本毛織株式会社のメセナ活動のひとつでもあります。
ニッケコルトンプラザの前身は、日本毛織中山工場でした。
その一角には、工場時代の女性従業員の守り神様として伊勢神宮より御神体を賜ったという神宮社があり、
当時から茂る樹木と共にひっそりと佇んでいます。
日本毛織株式会社では、「ニッケ鎮守の杜プロジェクト」を設け、残された自然環境を生かし、
手仕事に恵みを与えてくれる植物を育む庭づくりを行っています。
「galleryらふと」はこの庭園内にあり、「工房からの風」は、
この庭園を中心とした年に一度の大きな文化催事となっています。
◆2024年度開催にむけて
コロナ禍の中にも、規模や方法を工夫しながら「工房からの風」は開催を続けてきました。
2023年には、出展作家の展開はほぼ通常開催として実行いたしました。
2024年は、出展作家の事前準備を昨年以上に充実させるほか、ワークショップ、食品販売ブースなども復活させて、より広やかにご来場いただける内容を企画しています。
2024年 第22回「工房からの風 craft in action」応募要項
開催日: 2024年10月26日(土)27日(日)10時〜16時
応募期間: 一次募集2023年12月1日(金)〜12月20日(水)着
(二次募集は、2024年3月を予定しています)
応募資格:
・展覧会として充実した作品内容、点数を当日に出品し、展示販売ができる人。
(目安として、1800mm×3600mm程のスペースで、2日間充実した作品展示ができること)
・会期中、会場で自らのブースに滞在し、搬入、搬出を自らできる人。
・野外展であることを認識の上で展示構成ができる人。
・趣味としての制作ではないこと。 作り手本人の作品であること。
・作品は展示販売を中心とした構成を組むこと。
・今回が「工房からの風」に初出展となる場合、開催当日が50歳未満であること。
・日本国内在住であること。
・2024年10月19日(土)〜11月4日(月・祝)に、個展または大きなグループ展、クラフトフェアなどへの出展がないこと。
・2022年、2023年の「工房からの風」に出展した作家は応募いただけません。
応募方法:
1-応募カテゴリーをお決めください。
A ・「ニッケ鎮守の杜」エリアでの出展(悪天候などで、やむを得ず場所が変更する場合があります)
B ・ 出展エリアを一任(「コルトン広場」または「ニッケ鎮守の杜」など)
2-応募期間中にweb登録を行ってください。(困難な方は郵送のみでも可)
3-以下のものを送付ください。
a・記入済みの 応募用紙
b・作品写真
(制作内容が伝わり、かつ出品予定の作品に近い1年以内に制作したもので6~10枚程度)
c・84円切手
出展料:
出展料として33,000円を開催前にお納めいただきます。
納付時期はあらためてお知らせします。8月以降を予定しています。
主催者への納金は行わず、全額出展者の管理とします。
注意事項:
・A4以内の封書で送付ください。
・メールやCDなど、デジタルデータでの受付はしておりません。
・写真の返却はいたしません。
・個々の選考結果へのコメントは一切できませんことをご了解の上ご応募ください。
・テントは当方で設置いたします。(無料)
・会議テーブルのリースを承ります。(有料)
・コロナ禍や天災など、やむを得ない状況により中止となる可能性があります。
・食品の募集は行っておりません。
一次結果発表: 2023年12月中に結果通知を投函いたします。
※一次で選外となられても、二次への応募は可能です。
◆応募・お問い合わせ
〒272-0015 千葉県市川市鬼高1-1-1 ニッケコルトンプラザ管理事務所内
「工房からの風」係 tel. 047-370-2244 fax. 047-378-3555
director's voice
コメントする
庭に集う
今年度の「工房からの風」(10月28日(土)29日(日)開催)へ応募いただくための要項を公開しております。
→ click
3月15日から31日必着です。
郵便配達が以前よりも遅くなっていますので、お早目のご準備をおすすめいたします。
また、出展が適していると思われる作り手の方をご存知でしたら、ぜひ情報をご案内くださいませ。
豊かな第21回「工房からの風」を皆さんと創りあげたいと希っております!
3月に入って庭の手入れの日。
庭全体はまだ冬の名残りでさびしい雰囲気ですが、ひとつひとつ花が開いてきています。
ささやかな音色から、春爛漫、そして夏へと向かって、徐々に音量が豊かになっていく。
そんな目覚めを感じさせてくれる春の庭。
「工房からの風」の会場の一部「ニッケ鎮守の杜」(その中に、「手仕事の庭」という空間があります)の手入れは、私たち「工房からの風」「galleryらふと」スタッフが事務局となって運営しています。
具体的には、「工房からの風」のメインビジュアルを描いてくださっている大野八生さんに全体構成のアドバイスをいただき、月に3日ほど実際にお庭に入っていただいています。
そして、庭人さんとお呼びしている15名ほどの地域にお住いのボランティアさんが、共に庭作業を行ってくださっています。
(ちなみに、5月から新年度になり、新規庭人さんの募集も行います。
→ click)
庭人さんと一緒に作業着で庭の手入れをしていながら、「庭」という言葉の豊かさについて考えていました。
自然そのものである草木。
その草木のままであれば、山野や草原。
けれど、庭という空間には、人の意思と行動が自然と結びついて姿を成している。
まるで工藝のようですね。
自然素材と人の想い(デザイン…)と手の技が結びついて成したかたち。
そして、庭では、さまざまな草木(そして虫やいきものたちも)が影響し合って育まれていきます。
コロナ禍のこの3年間。
新たに世に出ていこうとしていた作り手たちは、出会いの機会の消失の中で、必死に模索してこられたのではないでしょうか。
自らを発露するために、SNSなどを活用してこられた方も多かったことでしょう。
たとえば小さな植木鉢の中で、一生懸命花や実をつけようと励んだように。
今年、「庭」に出てこられませんか?
工房で蓄えてきた力を持った作り手たちが、庭に集う。
集ったことで、影響を受け、与え、成熟に向かう。
そんなイメージを抱いて。
ホースで水撒きをしながら、「工房からの風」という野外展が、庭づくりと響き合って存在していることが、不思議なくらい必然に感じられたのでした。
一年を通して、庭人さんたちと共に育んでいる庭。
そこに、全国からはるばる集ってくる瑞々しい作り手。
そんな年月が、20年以上も続いてきたこと。
小さな奇跡の集積が、この時空を存在させてくれている。
21回目の「工房からの風」。
豊かな出会いをこの庭で叶えていただけまうように。
水撒きで出現!した虹。
新しい季節の始まりを祝福してくれているようでした。
director's voice
コメントする
選考結果を投函しました
今秋開催の第20回「工房からの風」へ、多数のご応募をいただきありがとうございました。
また、募集に際して、情報拡散やご紹介をいただきました方々へ、この場からも御礼申し上げます。
企画を担当する「gallery らふと」スタッフで拝見し、鋭意選考をさせていただきました。
北海道から沖縄まで広やかな地域からご応募をいただきました。
今回は、いつも以上に熱のこもった応募用紙が多く、こちらも読みこみに熱が入りました。
本日、選考結果を郵便で投函いたしました。
現在、到着まで2,3日以上かかるようですので、今しばらくお待ちくださいませ。
金曜日の配達でも届かなかった場合は、事務局までお尋ねくださいませ。
→ mail
選考通過をされた作家の方々。
今年は準備期間がすでに4か月を割っています。
さっそく、ふくらませた出展構想を、実現に向けて始動いただきたいと思います。
準備万端となるようにお進めください。
やりきった!出展してよかった!と思える結果を、ぜひ、体験していただきたいのです。
その起点とは、ご自身の制作そのものです。
:::
ここからは、ディレクターの個人的な感想を。
今回、今までで最も実力確かな作り手、その作品が集まる「工房からの風」になるかと思います。
その理由の一つに、出展経験作家の割合が全体の半分近くになっていることがあげられます。
これは、今までになかった割合です。
20回の記念展ということもあり、また、コロナ禍で作家も工房に籠って過ごした年月が長かったからでしょうか、
すでに個展などで活躍中の実力作家のご応募が、いつも以上に多くありました。
蓄えてきた実力に新鮮な風をそよがせて、新たな気持ちで出展くださることを期待しております。
複数回出展作家がいつもより多い、とはいえ、30名以上は初出展作家となります。
(全部で57名の選出をしております)
コロナ禍以前のようには、準備期間の熟成がしづらいことはありますが、
力のある作家の方々と一緒に出展する機会は、きっとこれからの糧になると思います。
:::
出展経験のある方にも、選外通知を多数お出しする結果となりました。
お顔を存じ上げている方々ですので心苦しさはありますが、
全体のジャンル構成も鑑みて、冷静にフラットに選考をさせていただきました。
今後、双方の機が熟してまたご一緒させていただければと存じます。
:::
「工房からの風」は出展することが目的ではない、と考えています。
出展して、そのあと、どのようにお仕事を展開するか、できるか。
そこまでを想い描いて、選考もさせていただいています。
選考通過がゴールではありません。
満を持して出展して、その後の制作活動につなげていただきたいと思っています。
その考えのもとに、作品には魅力があるのだけれど、機が熟していないと感じて、選外通知をお出しした方もいらっしゃいます。
時に「勢い」というのも大切ですが、勢いだけで出展して終わってしまうのはこの会の趣旨と異なります。
ぜひ、一層制作に励まれて、「工房からの風」への出展経験が、その後の制作活動への「追い風」になるようにと願っています。
:::
最後に。
いずれにしても、完全な選考などありません。
スタッフとともに精一杯読み込み、検討いたしますが、力のある方に選外通知をお出ししていることも多々あるかと思います。
私たちの目の未熟さを自覚しつつ、今年の「工房からの風」の構成をよりよいものにしようと努めています。
選外になられた方も、ぜひ開催当日、ご自身の目で会を見ていただければと思います。
その上であらためて出展希望をお持ちいただいた際には、またぜひご応募ください。
季節は真夏に向かいます。
10月29日30日、秋の実りを多くの方々と喜び合いたいと願います。
今年の「工房からの風」、ご期待ください。